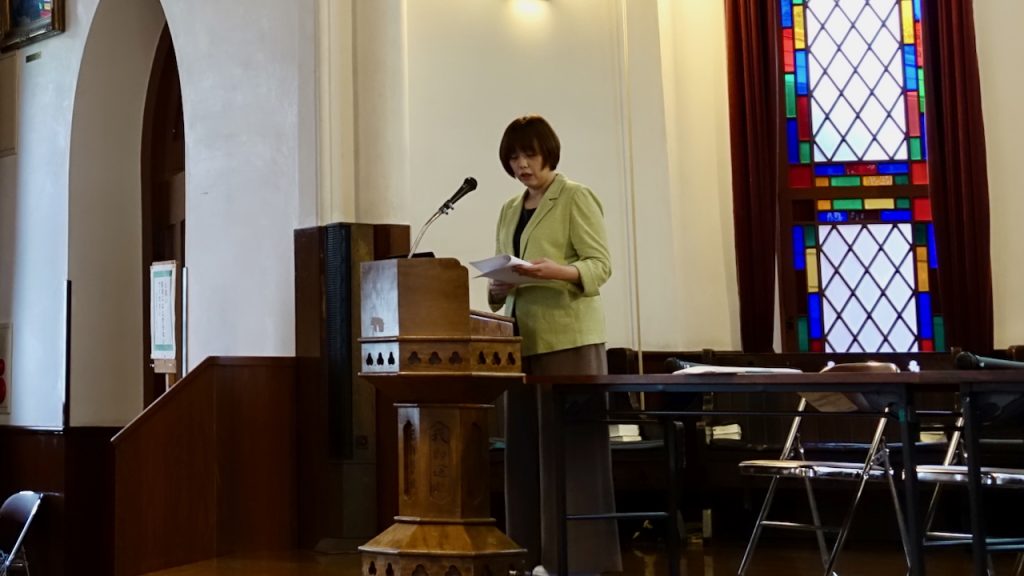公開シンポジウム「同志社の新しい形──その歴史的経緯とこれから」 (シリーズ「同志社150年の歴史から展望する未来への挑戦」第6回)
講師
沖田行司(びわこ学院大学学長、同志社大学名誉教授)
神田朋美(同志社女子大学嘱託講師)
司会
小原克博(同志社大学 学長、良心学研究センター長、神学部教授)
コメンテーター
飛龍志津子(同志社大学 生命医科学部教授)
朝田邦裕(同志社大学 広報部長)
趣旨
良心学研究センター主催の連続シンポジウム「同志社150年の歴史から展望する未来への挑戦」の6回目となる標記シンポジウムは「二校地問題と大学の大衆化」(1981〜2003)と「新設学部の展開」(2004〜現在)に焦点を当てます。
来年2026年、京田辺校地開校40周年を迎えます。ゆとりのある教育研究環境や学生数の増加を求めて田辺校地(当時)の建設計画が始まりましたが、それによって、どのような新たな教育や研究を目指そうとしたのでしょうか。田辺移転問題は学生運動の変化を映し出しています。学友会が解体される2004年までは、田辺移転反対の声が学生から出ていました。しかし、その後、学生運動は衰退の一途をたどり、学生が大学や社会に対し主体的に意見を表明する機会も失われていきました。「自治自立」の学生像の変遷にも着目します。
大学進学率が向上し、大学の大衆化、大学に対する社会的ニーズの多様化が進む時代の中で、1991年、大学設置基準の大綱化がなされました。文部省の大学に対する規制が緩和され、多くの大学で一般教育科目が削減されました。同志社大学においても、語学や体育は大きな影響を受けましたが、それは教育理念に対し、どのような影響を与えたのでしょうか。また、大綱化以降、表面的には規制緩和の様相を呈していますが、実質的には、文科省による大学管理の姿勢が強化されている状況の中で、私学・同志社はどのような位置を占めるべきなのでしょうか。
2004年以降、新しい学部が次々に作られ、かつての6学部体制から14学部・16研究科へと移行し、それが同志社大学の「新しい形」をなしています。これまでの歴史的経緯を十分に踏まえながら、総合大学としての同志社大学が、今後、激動の時代をどのように進むべきかについても自由に議論したいと思います。
講演の後、司会者および2名のコメンテーターを交えたパネルディスカッションを行い、最後にフロアーの参加者とも質疑応答の時間を持つ予定です。
関連するシンポジウム・文献
公開シンポジウム「歴史を振り返ることの意義──同志社創立150周年を見据えて」(シリーズ第1回、2024年3月4日)
公開シンポジウム「同志社草創期はどのような時代であったのか──新島襄の挑戦」(シリーズ第2回、2024年6月3日)
公開シンポジウム「新島襄没後の同志社の混乱と発展──志を継ぐ者たちの奮闘」(シリーズ第3回、2024年9月24日)
公開シンポジウム「戦争と同志社──キリスト教主義学校の苦悩と教訓」(シリーズ第4回、2024年12月20日)
公開シンポジウム「同志社の再建と学生運動の時代」(シリーズ第5回、2025年3月26日)
良心学研究センター編『同志社精神を考えるために』2023年(Kindle版)